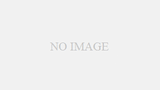ネットやSNSでの書き込みによる企業への誹謗中傷が増える中、知らず知らずのうちに名誉毀損や業務妨害、侮辱罪といった法的トラブルに発展するケースも少なくありません。これらの行為は、企業の信用を損なうだけでなく、投稿者が刑事・民事責任を問われる可能性もあります。今回は、企業に起こり得る主な法的リスクを中心に、それぞれの罪の違いと成立条件、実際に対処する際のポイントを解説します。
名誉毀損罪とは?事実でも成立する“信用への攻撃”
名誉毀損罪は、企業に対する誹謗中傷の中でも、特に多くのケースで適用される法律上の罪です。刑法230条に定められており、「公然と事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させる」ことで成立します。ここで重要なのは、事実であっても、名誉毀損が成立しうるという点です。
たとえば、「この会社は過去に行政指導を受けていた」「従業員が不祥事を起こした」といった事実があったとしても、それをあえて不特定多数の人に向けて投稿し、企業の社会的評価を傷つけた場合、名誉毀損罪に該当する可能性があります。
ただし、以下の3つの条件がすべて揃えば、違法性が阻却される(=名誉毀損には当たらない)とされます。
- 公益目的がある
- 内容が公共の利害に関する事項である
- 真実性または相当な理由による信頼性がある
この「違法性阻却要件」に該当しない限り、たとえ事実でも名誉毀損が成立します。たとえば、事実を歪めて伝えたり、公益性のない暴露であったり、悪意をもって繰り返されたりすれば、犯罪とみなされる可能性が高くなります。
企業側としては、名指しでの事実暴露や攻撃的なレビューが見つかった場合、「それが事実かどうか」に加えて、「公益性があるかどうか」「社会的評価を著しく損なっているか」を軸に法的対応を検討する必要があります。
業務妨害罪とは?営業活動を妨げたと認められる条件
業務妨害罪は、名誉毀損と並んで企業が被害を受けやすい刑事リスクのひとつです。刑法233条および234条に定められており、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて他人の業務を妨害した者」は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
たとえば、以下のようなケースが業務妨害罪に該当することがあります:
- 「この会社は詐欺をしている」など根拠のない悪評をSNSで流す
- 偽のクレームや問い合わせを大量に送る
- ネガティブなレビューを意図的に繰り返し投稿する
- 掲示板などで「この会社に電話攻撃を」などと呼びかける
こうした行為は、企業の営業活動や顧客対応に直接的な悪影響を与えるものであり、違法性が高く、悪質であれば刑事事件として扱われることも珍しくありません。
一方で、単なる口コミや不満の表明が即業務妨害に該当するわけではなく、「業務が実際に妨害されたかどうか」が判断の鍵になります。企業への問い合わせ件数の増加、売上の減少、クレームの頻発など、具体的な業務への影響があれば、違法性を裏付ける証拠となり得ます。
企業としては、「拡散されて困った」という主観だけではなく、「業務上のどんな支障が生じたか」を証拠として蓄積しておくことで、法的対応への道が開けます。早期の記録と被害状況の可視化が、業務妨害対策の第一歩になります。
侮辱罪の特徴と「言葉遣い」が法的リスクになる境界線
ネット上の発言には攻撃的な言葉や感情的な表現が飛び交うことも多く、こうした“言葉そのもの”に対して成立するのが「侮辱罪」です。刑法231条に定められており、名誉毀損とは異なり事実を示さなくても成立するのが特徴です。
具体的には、以下のような表現が侮辱罪に該当する可能性があります:
- 「あんな会社はクズだ」
- 「バカな経営者がやっている」
- 「あんな店は潰れて当然」
- 「存在価値がない会社」
これらは明確な事実を示していないものの、企業やその関係者に対して社会的な評価を下げる言葉として、法的責任が問われる場合があります。
侮辱罪は軽犯罪とされがちですが、令和4年に法改正が行われ、拘留または科料のみだった法定刑が「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」に強化されました。これにより、ネット上の侮辱的な書き込みに対する処罰のハードルが下がったといえます。
重要なのは、発言者の意図よりも、「その言葉が第三者から見て企業の社会的評価を下げるかどうか」が判断基準になるという点です。企業としては、軽視しがちな侮辱的な投稿にも注意を払い、積極的に証拠を保存しておく必要があります。
企業が法的リスクに対応するために準備しておくべきこと
名誉毀損、業務妨害、侮辱罪――いずれも企業がネット上で被る可能性のある深刻な法的リスクです。こうしたトラブルに巻き込まれた際、迅速かつ正確に対応できるかどうかは、事前の準備と対応体制の有無にかかっています。
まず、最も重要なのは「証拠の保全」です。問題となる投稿が確認された時点で、URL・投稿日時・スクリーンショット・SNSアカウント情報などを正確に記録しましょう。削除されてしまう前に、法的対応のための材料を整えておくことが不可欠です。
次に、「誰がどのように対応を主導するか」を明確にしておくことも大切です。社内での初動対応フロー、広報や法務との連携ルート、外部弁護士や専門会社への相談体制などを整えておくことで、無用な混乱や情報の錯綜を防ぐことができます。
さらに、万が一訴訟や刑事告訴を検討する場合には、ネット誹謗中傷に強い弁護士の確保が不可欠です。IT分野に精通し、対応実績のある専門家と連携することで、削除請求・開示請求・損害賠償請求といった選択肢をスムーズに取ることが可能になります。
そして何より大切なのは、被害が起きる前に予防の意識を持つことです。社内外への情報発信を丁寧に行う、顧客対応に注意を払う、レビュー管理を行うなど、地道な信頼構築が風評被害のリスクを最小限に抑える鍵となります。
まとめ
企業はインターネット上で、名誉毀損・業務妨害・侮辱罪といった多様な法的リスクにさらされています。これらの行為は、投稿者にとっては“意見”のつもりでも、内容や影響次第では違法と判断され、企業の信用と業務に甚大な被害を与える可能性があります。企業側は、投稿の内容や拡散状況に応じた迅速な対応と、日頃からの備えを整えておくことで、こうしたリスクから自社を守る体制を構築することが求められます。